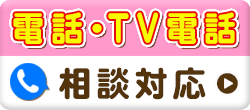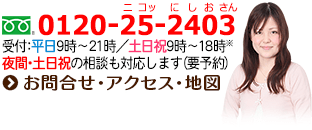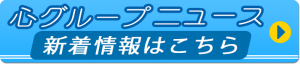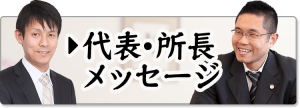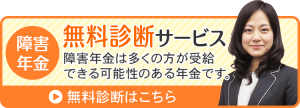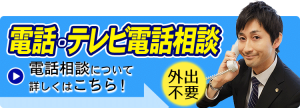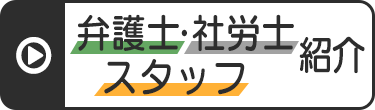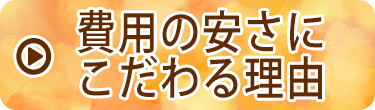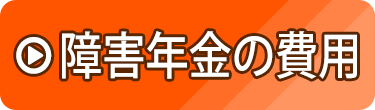障害年金の受給要件
1 受給要件の原則は障害の残存と保険料の納付
障害年金には、国民年金加入者への障害基礎年金、厚生年金加入者への障害厚生年金、共済年金加入者への障害共済年金という種類がありますが、いずれも基本的な受給要件は共通しています。
それは、障害が残存していることと、各年金の保険料の納付要件を満たしていることです。
これらの要件を満たしているかについては、日本年金機構が審査します。
2 障害認定日において等級基準を満たす障害が残存していることが必要
障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関で診療を受けた日を「初診日」と言います。
この初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内であってもそれ以上回復の見込みがない状態(症状固定)に至った日を「障害認定日」といいます。
障害年金が支給されるかは、この障害認定日において、国が定める等級認定基準を満たしているかどうかによって決まります。
この障害等級については、医師が作成する診断書等をもとに審査されます。
障害等級は1級と2級があります。
障害基礎年金の場合、2級以上に認定されないと年金は給付されません。
各等級に細かい認定基準がありますが、目安としては、障害により日常生活に著しい制限があるかというのが2級の認定基準とされています。
なお、障害厚生年金、障害共済年金では、2級より軽度の3級の認定基準が設けられています。
3 保険料の納付要件
障害年金の受給要件として、保険料の納付がされているかという受給要件があります。
基本的には、「初診日の月の前々月までの年金加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること」「初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」という要件を満たす必要があります。
ただし、20歳前に障害を負った人の場合、国民年金保険料の納付義務を負っていないため、納付要件を満たさなくとも障害年金を受給することができる場合があります。
また、初診日が65歳以降であっても、厚生年金加入者、共済年金加入者は障害年金を受給することができる可能性があります。
4 受給要件を満たしているかは専門家にご相談を
障害年金の受給要件は複雑であり、ご自分が要件を満たしているか判断することは困難な場合があります。
特に、障害等級を満たしているかどうかについては、法律的な判断が必要になりますので、専門家に相談して確認することをおすすめします。
私たちは、そのような障害年金の受給要件を満たしているかどうかを無料で診断する「障害年金無料診断サービス」を行っていますので、障害年金の申請の際には、まずは私たちにご相談ください。
また、等級認定を受けるためには、法律的な観点を意識して、医師に適切な診断書を作成してもらう必要があります。
私たちに障害年金の申請についてご依頼いただければ、障害年金の書類の準備について多くをお任せいただける他、医師に診断書を作成してもらう際のポイントについてアドバイスを行うこともできますので、千葉で障害年金の申請をお考えなら、私たちへご相談ください。